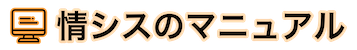「デジタル」は物理的なモノがないため、コピーや流通が容易なのはご認識の通りです。
しかし、そうした特性があるがゆえに、何の権利を購入しているのか?が問題になります。
特に、個人で利用するような電子書籍、映画、ゲームのようなコンテンツは、定期的に話題になります。
今回のメルマガでは、こうした「デジタルの権利」について見てみましょう。
何を購入しているのか?
電子書籍等は、結局は、そのストアにあるコンテンツへのアクセス権を与えているにすぎません。
ストアの閉鎖や、何かしらの理由で当該コンテンツが削除されてアクセスできなくなることがあり、
消費者からすると「購入したのに」という感覚になります。
こうした状況を鑑み、上記のような特性がある販売について「購入」と使ってはならない、という話も出てきています。

金額に違和感があるのも、問題となる理由の一つか
たとえば、Kindleのような電子書籍。
おおよそ、紙の本と価格は同じです。
ゲームも同様です。
むしろ、ダウンロード版よりもパッケージ版の方が安く入手できることがあります。
紙の本やゲームパッケージがあれば、貸すこともできれば、売ることもできます。
突如、運営側の都合で使えなくなるようなこともありません。
「いきなり使用できなくなるかも」という大きなリスクがあるにも関わらず、
電子版と同じような価格であるというのが
苛立ちを覚える一つの要因で、
実際にストア閉鎖などが発生した時に大きな騒ぎとなる理由かと思います。
「利便性」と「権利の範囲」で価格が決まればよいのか?
今のところ「ズバリ」な解はないのですが、
納得のいくバランスが取れればよいのかなとも感じます。
例えば、ストアが閉鎖したら払い戻すという内容であれば、そのリスクに応じた値段とする。(今の定価に近い値段でよいのでは)
サービスが終了したらオシマイ、であれば、その分安くする。
逆に、デジタルの利便性に高い価値があるのであれば、安くなくともよいでしょう。
※個人的な意見ですが、
PCゲームプラットフォームであるSteamはPlayStationなどと異なり、
Windowsがある限り長くプレイできるでしょうし、
複数のどのPCでもプレイできる、と、利便性が高いと感じています。
そのため、ゲームを購入する時はSteamで購入するようにしています。
もちろん、それぞれのリスクを考えた保険のような仕組みも必要で
(ストア閉鎖=倒産、もありますし)、
経済的に成り立たないようなケースもあるとは思います。
ただ、
「他の購入手段との違いに、それ相応の値段の違いがあること」
という状態であり、
内容を理解して支払していれば大きな問題にはならないのではないでしょうか。
今でも、映画の購入で
7日間レンタルだと300円、買い切りだと3000円、といったケースがあります。
こうした形であれば、きちんと判断して購入するのではないでしょうか。
(この「買い切り」が、未来永劫という意味合いでないということが、
冒頭の問題に戻るわけですが。)
「購入」したものは、所有権が本人に移動するという感覚が一般的だと思います。
その点に食い違いがでるのも、「購入」という言葉が難しい点かなと感じますね。
※でも、Kindleで「レンタル」ボタンだと、紙の本を買ってしまいそうですよねぇ、、、
メルマガ『Professional's eye』
"意見が持てる"デジタルコラム
週1回配信、3分で楽しめます。
送信いただいた時点で「Privacy Policy」に同意したとみなします。
広告を含むご案内のメールをお送りする場合があります。